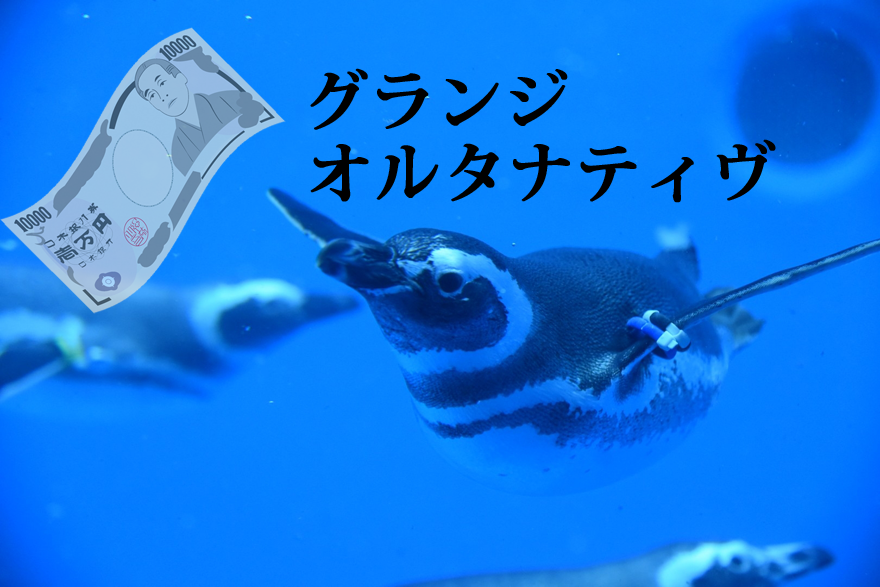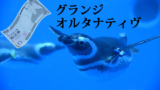Smashing Pumpkins 37曲 (You Tube)
Smashing Pumpkins (スマッシング・パンプキンズ)の概要
1985年から1988年までThe Markedというバンドで活動していたビリー・コーガンを中心にシカゴで結成されたバンド。
グランジという言葉とともに語られるためかシアトル出身だと勘違いされることもあるが、Sub Popからシングルを一枚リリースしたことがあるぐらいで、シアトルとはほとんど縁がなかった。
このバンドの音楽性は「Black SabbathのリフとCheap Trickのメロディと感受性の強い歌詞を持つオルタナ・バンド」というのが的をえた表現だと思う。
あとはプログレを連想させる曲展開、サイケデリック、夢見心地なバラードなど。
80年代のニュー・ウェーヴやエレクトロからの影響も感じさせる。
ただしパンク、特にTalking Headsなどのニューヨーク・パンクのことは嫌悪していた。
陰鬱をシャウトで吐き出していた他のバントと違い、悲しみをメルヘンチックに歌い上げるといったところだろうか。
1991年5月にリリースされたデビューアルバムであるGishが好評を得てCMJチャートで1位となりツアーの客入りも順調だったのだが、同年秋にリリースされたNirvanaのNevermindがブレイクするとグランジ・ムーヴメントに巻き込まれてしまい、便乗バンド呼ばわりされたこともあったようだ。
ニルヴァーナが出てくる前は僕たち「レトロ・バンド」って思われていたんだ。
そしてニルヴァーナが出てきた後は「便乗バンド」さ。
つまり僕たちは過去からもかっぱらい、未来からもかっぱらったってわけ。
どうでもいいけどさ。元々メディア・コントロールはあんまり得意じゃないから。
ビリー・コーガン / ロッキングオン1996年3月号
またポップな音楽性やパフォーマンス、活動内容が名声を追い求めているロックスター志向という印象を与えてしまうことがあり、特にそれを嫌うインディ界隈から非難されることもあった。
(Gishの頃を振り返って)とにかく目立ち過ぎ、やり過ぎ、名声欲あり過ぎってことになった。
インディーズ界から見れば、パンプキンズはインディーズになり切ってない。
ところが、ノーマルな界隈じゃ僕らは「あまりにもヘヴィ」って言われちゃう。
メジャー・レーベルに至っては気にも留めてくれない。
つまり、中途半端な存在になってたんだ。
ビリー・コーガン / クロスビート2000年8月号
ブーム真っ只中の1993年にリリースされた2ndアルバムSiamese Dreamが400万枚をこえる大ヒットとなり、またロラパルーザにも出演しシーンを代表するバンドの一つとなった。
しかしビリー・コーガンはSiamese Dreamのような音楽性に限界を感じていたようで、それを打破してバンドの限界を超える手段として、3rdアルバムを2枚組にして様々なスタイルの曲を収録することでバンドを成長させようとした。
カート・コバーン死後の1995年にリリースされた3rdアルバムMellon Collie and the Infinite Sadnessでは、そのバンドの成長と商業的成功を両立させることに成功した。
数多くの賞を受賞し、名実ともにオルタナティヴ・バンドの代表格となった。
この辺りのことはカート死後のUSオルタナ3大バンドも参考にして欲しい。
だがすべて順風満帆とはいかず、1996年7月にツアーでキーボードを担当していたジョナサン・メルヴォインがホテルの一室でドラッグの過剰摂取で死亡するという事件が起きた。
バンドは同室にいたドラマーのジミー・チェンバレンを解雇するという決断を下した。
ドラマーを失い3人編成となったバンドが次に進んだのは従来のロック、特にハードロックを捨て去って、エレクトロサウンドを積極的に取り入れアコースティック色やニューウェーヴ色を強く反映して新機軸を打ち出すという道であった。
1998年にリリースされた4thアルバムAdoreでは、大ヒットした作風を自ら壊し、その上で傑作を作り上げるという、オルタナティヴという言葉を体現するかのようなことを成し遂げた。
僕らはニュー・パンプキンズを見つけるために、オールド・パンプキンズを手放さなきゃいけなかったんだ。
これは、新しいパンプキズヘの入り口なんだよ。
古いパンプキンズを見ると、「ギッシュ」「サイアミーズ」「メロンコリー」はセットになってる。
で、新しいアルバム(Adore)は、ニュー・パンプキンズの第1号アルバムになってるってわけだ。
ビリー・コーガン / クロスビート1998年6月号
AdoreはSmashing Pumpkinsの第2章の華々しい幕開けとなるはずだったのだが、日本とヨーロッパではそれなりの評価を得たものの、本国アメリカではメディアから酷評され売り上げ不振につながってしまった。
この出来事はオルタナの敗北を意味しており、ビリー自身もショックを受けたようで、2000年の解散表明へとつながってしまう。
オルタナ代表バンドの動向とオルタナの敗北、少数派に戻ったオルタナに詳しく書いたので読んで欲しい。
「アドア」への反応は、バンドが耐え得る最後の傷だったような気がする。
傷はいつでも覚悟してきた。相手がインディーズ、メジャー、プレス、何だろうがね。
ただ「アドア」の件だけはもういいやって感じだったんだ。まるでつまはじきさ。
同世代の罪の償いをしろと言われてる気がした。
カート・コバーンは自殺して、パール・ジャムはビデオ制作をやめてツアーもしなくなってきてた。ホールはどうもハッキリしない。
そんな中でパンプキンズはツアーもしてアルバムも作ってた。
ところが、オルタナバンドとして頑張ってるってことで逆に罪を着せられたんだ。
それはないよね。悪いのはジェネレーション全体だよ。
「アドア」はオルタナが世間の期待に沿わなかった失望感のはけ口にされたんだ。
ビリー・コーガン / クロスビート2000年8月号から引用
だが解散理由はこれだけではないようで、「本当に複雑で理由は100万個ある」とのこと。
2004年になってビリーが「バンドを解散させたのは(ギターの)ジェイムズ・イハだ。」と発言したように人間関係の悪化も見え隠れし、ドラマチックな終焉を迎えたわけではないのかもしれない。
話しは前後するが、Adoreリリース後に解散を決意したものの公には発表されなかった。
解散前にアルバムを制作するという決定をし、ドラマーのジミー・チェンバレンを呼び戻してアルバムMachina/The Machines of Godを制作した。
だがレコーディング中にベースのダーシー・レッキーが脱退。
脱退理由は彼女が演技の道に進むためだとか言われていたが、当時のビリーは明確に説明しなかった。
後に語られたところによると、ドラッグ依存症だった彼女がドラッグ厚生施設への入所を拒否したから解雇したとのこと。
アルバムリリースから約1か月後の2000年3月に解散を発表した。
解散後のビリー・コーガンの活動としてはZwanというバンドとソロアルバムのリリースがあった。
どちらも音楽性と当時のビリーの発言から、Smashing Pumpkinsを連想させるような音楽にならないように無理して努力した様子がうかがえる。
だが、2005年のソロアルバム発売日に地元シカゴの新聞広告上でSmashing Pumpkinsを復活させると宣言。
オリジナルメンバーは再結成に参加するのかどうか情報が流れてこなかったのでファンをやきもきさせたが、結果的にジミー・チェンバレン以外のメンバーは参加せずにほぼ2人で制作された再結成アルバムZeitgeistが2007年にリリースされた。
(解散から学んだことについて)僕とスマッシング・パンプキンズを切り離すことはできないんだと悟ったよ。
最初に解散した当時は、とにかくあのバンドにうんざりしてたし、僕を放って置いて欲しいという一心だった。
だから解散したのに、世間の人たちはいつまでも僕とあのバンドを切り離して考えてくれなくてさ。
ひどくストレスを感じたけど・・・でもよくよく考えた結果、結局僕自身がスマッシング・パンプキンズのパーツのひとつなんだと気づいた。
そんな風に気づいたこと自体、また新しいストレスになったけどね。
でも、それを受け入れることで、ようやくバンドと自分との関係が見えてきたんだ。
僕はビリー・コーガン=スマッシング・パンプキンズ、なんてこれっぽっちも思ってないんだよ。
とはいえ、スマッシング・パンプキンズという世界を作ったのは僕自身なわけで・・・おもちゃのブランドみたいなものかもね。
自分が作ったこの世界から一歩外へ出ると、僕は世間からうちのめされ、何もできない負け犬のような気分にさせられる。
結局、スマッシング・パンプキンズこそ僕の帰るべき家だったんだよ。
今はとても心地好いし、安らぎを感じる。
ビリー・コーガン クロスビート2010年10月号
2009年にはジミーの脱退が発表されオリジナルメンバーはビリーのみとなってしまったが、Smashing Pumkinsとして活動を続け、ウェブ上で曲を発表するプロジェクトを立ち上げたり、2012年と2014年にはアルバムをリリースした。
Smashing Pumpkinsが一度解散してからこの時点で約15年間が経過していたが、ビリーは過去のSmashing Pumpkinsとの狭間の中で苦しんできた感がある。
新作を発表するたびに過去の名作と比較され、ファンの中には過去の名曲のような新曲ばかりを期待し新しい音楽性を評価しない人も多くいる。
「サイアミーズ・ドリームは最高の作品だ」と言われたら、僕の中に湧く感情があって、それは、「サイアミーズ・ドリームが最高」と言う言葉の中には、もうあんな作品は二度と作れない、君があんな風に注目されることはもう二度とない、という意味が込められているんじゃないかということ。
再び偉大な音楽を作るということを僕のファンが信じなくなったとき、両者の間の会話は、まったく異なるものになる。
つまり今のモチベーションに興味を持ってもらえなくて、「なんで昔の曲は演奏しないんだ」って言われる始末だし、今はもう優れたアーティストでもないのに、やるべきことをやらない厄介な人だという見え方になってしまうというね。
ビリー・コーガン ロッキングオン2012年8月号
2012年のアルバムOceaniaでは従来のスマパンと新しいスマパンを見事に融合した傑作となり、ようやく過去の呪縛から解放されたかに思えたが、実際はそうではなかったようだ。
2015年にはジミーが再びバンドに復帰。2018年には長年に渡ってビリーと確執のあったジェームズ・イハがバンドに復帰しアルバムも制作された。
ダーシー・レッキーのバンド復帰も模索されたが実現しなかった。
バンドは2020年現在も存続中だ。
関連リンク
Smashing Pumpkins (スマッシング・パンプキンズ)のアルバム紹介
おすすめアルバム
Siamese Dreamはバンドの代表作の一つ。
個人的にはMellon Collie and the Infinite Sadnessが最高傑作。
Adoreはニューメタルに敗れた悲劇のアルバム。
Oceaniaは再始動後の名盤。