コンニチハ、Sonic Youthのサーストン・ムーアです。
(ユー・ノウ・ユー・アー・ライトの)PVって終始カートの映像しかなくて、ちょっとがっかりしたんだよね。
ニルヴァーナと仕事したことある人ならだれでも言うと思うよ、「ニルヴァーナは正真正銘のトリオだった」って。
確かにカートの歌声、彼の発するオーラは特別だったと思うけど、あの3人が集まったときに生まれるエネルギーは別格だったよ。
それがあのPVには全く反映されてなくて・・・
クリスとかもさ、凄いヤツなのに。
だけどニルヴァーナの魅力って、やっぱりカートにあるんだろうね。
何しろ一つの世代を完全に虜にしてしまったんだから、カートの歌声は。 (ロッキングオン2003年5月号から引用)
やっと届いたNirvanaのNevermind 20th Anniversary Deluxe Edition。
詳細はユニヴァーサリーのNirvanaのディスコグラフィのページで。
まだディスク1の最新リマスターしか聞いていないんですが、まあその感想でも。
結論を言ってしまえば最悪、ニルヴァーナ=カート・コバーン・リマスターです。
再生した瞬間に直ぐわかるのは音が大きいなあと。
やはり音圧至上主義マスタリングをやってしまったかと悲しかったです。
こういうリマスターでは音圧が上がっただけで高音質になったと騙されやすいんですが、実際の音質はどうなんでしょうか?
聴き比べてみると音質もかなり違います。
旧盤よりも今回のリマスターの方がカートの歌とギターがクッキリしたような印象を受けます。
聞こえ難かった音も良く聞こえるようになっています。
恐らく中域の音を上げたんでしょう。
ですが、その弊害として犠牲になっているのがドラムとベースの音です。
デイヴのドラムは全く持って力強さが感じられません。
クリスのベースも輪郭はクッキリしてはいますが、ベースらしい重低音は埋もれ、厚みのある重低音ではなくなっています。
Drain Youなんかはそれが良くわかります。
だからニルヴァーナ=カート・コバーン・マスタリングだと思うわけです。
他の音を犠牲にしてでもカートの音を目立つようにしたんだなあと。
それに音圧競争、音圧至上主義(英語ではLoudness War)マスタリングなためか、旧盤よりもキンキンしています。
ですから、ORG盤の音を超えるどころか、旧盤CD以下の最悪なリマスターだと思います。
旧盤CDの音量を上げて聞いていた方が良いです。
96khz/24bitも配信されているので聞いてみましたが、同じニルヴァーナ=カート・コバーン・マスタリングなんで、96khz/24bitうんぬん以前の問題でダメ出しせざるをえません。
今回のリマスターを担当したのは、このブログでも何回か名前を出したことのあるBob Ludwig。
よくもNevermindをこんな風にしてくれましたねえ・・・
エンジニアとしては有名な方なんですが、結構音圧主義リマスターをやっています。
まあ本人はアンチLoudness Warな運動もされているようなんで、ユニヴァーサルの指示に従った、やらされたのかもしれません。
「良い音」とか「高音質」っていうのは個人の嗜好の問題。
あなたが聞いていて「高音質」だと思うなら「高音質」です。
私にとっては今回のリマスターNevermindは最悪の音です。
「最新リマスターで新たな命を宿す」とか「非常に音の広がりを感じられるようになり、奥行き感が出ている」とか、頭がおかしいんじゃねえかっていうw
まさかこのリマスターヴァージョンを今後の標準仕様にするんじゃないだろうな・・・
Nevermindを全制覇したわけじゃないですが、私にとって最強なのはやはり以前も紹介したORG盤。
最初は?って感じでしたが、聞けば聞くほど素晴らしい音です。
MFSL盤とSimply Vinylは聞いたことがありませんのでなんとも言えません。
日本のネット上の掲示板やフォーラムは全く検索に引っかかりませんが、海外の掲示板などを見ると、ORG盤、MFSL盤、Simply Vinylの評判は良いようです。
まあNevermindを聞くならアナログレコードがオススメですってことで終了します。
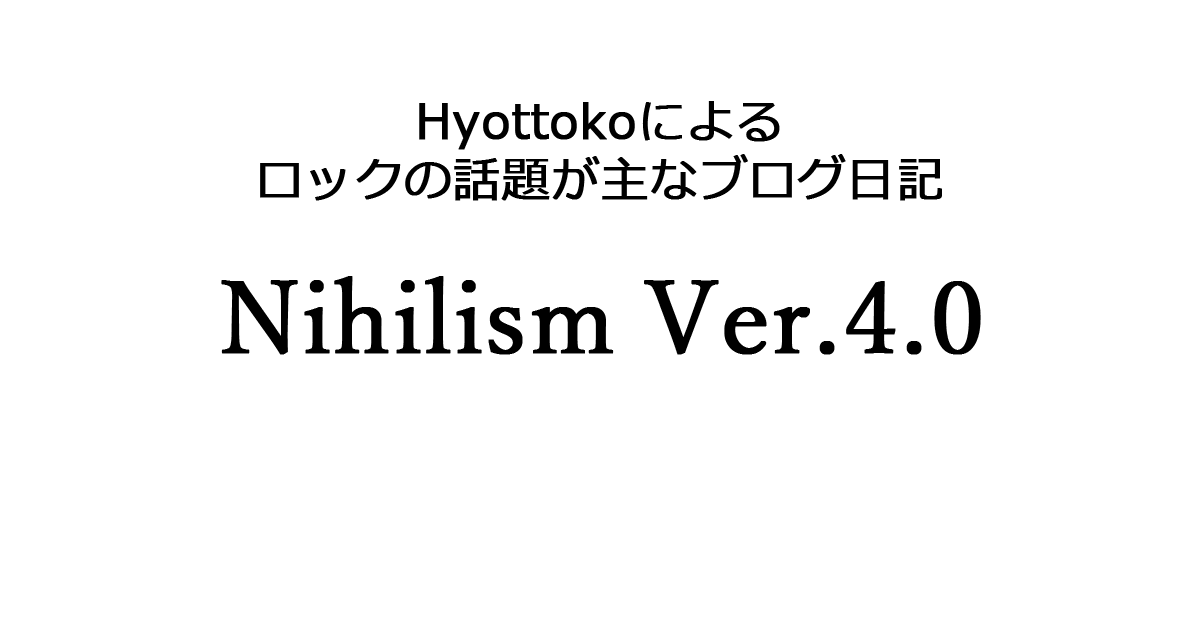
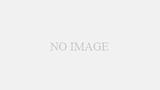
コメント
Nevermindも音圧至上主義に屈してしまいましたか・・・。危惧していたことが現実になってしまった感じです。とりあえず世間の評判を見てから購入を検討しようとしていたので、今回は購入を見合わせることにします。
音圧至上主義でマスタリングされた作品は、iPodとかだとパッと聴きでは良く聞こえたりすることもありますが、ある程度のオーディオ機器で聴くとどうにも聴き疲れしてしまうのがいやです。ある意味でピュアオーディオ泣かせと言えるのかもしれません。それに、ピークに張り付きっぱなしの音を長いこと聴かされると耳の健康にも悪いです。これが今後の主流になってしまうとしたら残念です。ユニヴァーサルジャパンがSHM-SACDでリリースとかしたらどんな音になるのかなぁ、なんてふと思ってしまいました。
余談ですが、Bob Ludwigが手がけたとあるバンドのリマスターは、過度の音圧競争に走らないアナログライクな音で楽しめました。そういう意味では、やっぱりレコード会社に音圧を上げるようにと指示されてやらされていたんでしょうね・・・。
こういうリマスター作品の日本のレビューは、音圧主義に触れているものは殆どないので、海外のレビューを参考にした方がいいですよ。
大抵iPodでしか音楽を聞いていなさそうな人とオーディオにある程度こっている人とが音圧主義に関して対立していることが多いんですがw
ですが、アメリカのamazon.comのレビューでは、今現在はLoudness Warという言葉と共に語られているレビューに対して「参考になった」と投票する人がそこそこ多いです。
最も期待したいのは音を極力いじらないというフラットトランスファーというコンセプトの元に制作されたSACDです。
実際のマスターテープはどういう音がするのかは関係者以外はわかりませんが、今回のリマスターは音をいじりすぎていると想像してしまいます。
はじめまして、いつも楽しく読ませていただいています。
Nevermindが24bitという事で私も楽しみにしていたのですが、正直期待していたものとは違いました。
しかし、Nevermindはコンプレスされていない音の形であるのが正しいのか?とも思うわけです。
昨年フィル・スペクター・プロデュースのジョージ・ハリスンのアルバムが24/96配信とアナログ盤のみで再発されたのですが、その音の良さとは別にそれがアルバムの最終形として正しいのか疑問にも思ったものです。
60年代のシングル盤は音圧高くデカイ音を目指してマスタリングされていたわけで、ポピュラーミュージックはフラット・マスターで聞ける音だけが正解じゃないとも思えます。
音圧高く、海苔波形だからダメとも言い切れないのかと思うようにもなりました。(銀杏BOYZのアルバム2枚はやりすぎで、アナログ再発の方が遥かに良かったですが)
もちろん答えは一つではないのですが、ひょっとするとNevermindはオリジナルCDぐらいの感じで存在するのが良いのかと思います。ボブ・ラディックもエンジニアとして腕も名もある人ですから、何かしら思うところあってこの音なんじゃないかと。
と言いつつ、個人的にはMFSLのアナログが一番しっくりくるのですが。
なかなかに難しいものです。
こちらこそはじめまして。
レコードの場合はコンプレッサーもあるのでしょうが、音圧を上げる場合は溝と溝の幅が大きく関わってくるようなので、CDの海苔波形とは意味合いが違うのではないでしょうか。
LPではなぜ音圧が低くてシングルでは音圧を上げることができるのかを理解しているつもりですが、60年代のシングルは所持していないので実際のところは良くわかりません。
レコード時代の音圧戦争は、アナログという制限があったためそれほど問題にはならなかったと読んだ記憶があります。
「正しい音」というのは人によって定義が違う難しい問題ですが、「バンドが当時望んだ音」として話を進めさせていただきます。
レコード時代は、ラッカー盤を制作するカッティング(マスタリング)という作業にバンド側が立ち会って音質をチェックしていたようです。
ですが、全ての国のラッカー盤のカッティングには立ち会わず、基本的に本国のカッティングにのみ立ち会っていたようです。
ですから、バンド側が当時OKを出した音は本国のオリジナル盤、厳密にはマトリクス1の真のオリジナル盤ということでしょう。
CD時代には、バンド側がマスタリングに立ち会っていたのかはよくわかりません。
Nevermindの場合、オリジナルレコード盤はDGC-24425のUS盤ということになるのですが、レコードが急速にCDに取って代わられた時代ということで、バンドがカッティング(マスタリング)に立ち会ったのかは疑わしいところではあります。
またIn Utero時のインタビューでは、マスタリングについてよくわかっていなかったというような発言を残しているので、マスタリングは人任せだった可能性が高いと思います。
ブッチ・ヴィグによると、アンディ・ウォレスがミキシングをしたものを当初はバンドは気に入っていたが、売れてから貶し始めたとのことです。
ですから、バンドが当時気に入っていた音は、ミキシングを終えたマスターテープ(マスタリング前です)と考えてよいと思います。
ですから、「正しい音」を「バンドが当時OKを出した音」とするならば、マスタリング前のマスターテープと言って良いと思います。
それをマスタリングで極力音を変えないフラットトランスファーでリリースするのが最善だと思います。
DGC-24425は入手困難なので所持していないのですが、90年代の他の作品のオリジナル盤とCDを聞き比べると、音質的にはさほど変わらないという印象を受けました。
また、マスタリングで音質を大幅に変える現在とは違って、「音質を決定するのはミキシングで、マスタリング時には音質を大幅に変えない。」というコンセプトが守られていたのでしょう。
ですからオリジナルCDは「正しい音」に近いと思います。
仮に今回のリマスターが、Primal ScreamのScremadellcaのように程よく音圧を上げただけ、Metallicaのリマスターのように海苔波形化しても音質的には大きな変化を感じられなければ、ここまで酷評することはなかったでしょう。
「音圧大きいな」ぐらいの文句で終わったと思いますw
ですが今回のリマスターは音質を変え過ぎですし、上述のようにそれが「バンドが当時OKを出した正しい音」とも思えません。
私は100%「バンドが当時OKを出した正しい音」信者ではないですが、今回の音質は私の好みってわけでもありません。
そういうわけで、私には「正しい音」でも「個人的に好きな音」でもないので、酷評せざるをえません。
はじめまして。いつも情報源として活用させてもらってます。非常に勉強になります。
この記事を読んで確認したのですが確かにDrain Youは顕著ですね。
バスドラのキック音が完全に殺されている。
Breedも少しその傾向があるような。
それ以外は自分的にはそこまで不満は無いというか、
Nevermindを今風・現代風に聞こえやすくしたらこんな感じになるのかなという印象です。
色々考えたんですがいくら近年リマスター技術が向上しているとはいえ九十年代前半の音楽を対象にすれば、
そもそもリマスター自体にそこまで力が無いと思うんですよね(六十~八十年代の音楽ならともかく)。
人間の視聴能力にも限界があるわけですし。
そういう場合例えばオリジナルを尊重したマスタリングをしてもたぶん
「これどこが変わったの?」と多くの人が思う気がするんですよね。
結局元との違いはマニアが相応のオーディオを使ってかなり集中して聞いた場合にしか分からない気がします。
それならパッと聴いて違いが分かるような商業的リマスターになってしまうのもしょうがないのかな~なんて思ったり。
俄仕込みで語ってすいませんw
こちらこそはじめまして。
90年代のCDは、CD特有のキンキンしているような感じはありますが、音は良いと思います。
だから無理にリマスターする必要もないと思います。
現在はマスタリングで音質を大幅に変えるのが主流のようです。
私も色々調べる前まではそれが当然だと思っていました。
ですが、本来マスタリングという作業ではなく、そういうことはミキシングの段階でやることだそうです。
ですから、リマスターという言葉を聞くと音質が大幅に変わると捉える人が多いと思いますが、そういうリミックス的リマスターだと思い込むのが間違っているとも言えると思います。
マスタリングという概念も昔と比べて大幅に変わってしまったようで、リマスタリングで音質が大幅に変わっていないと詐欺だと思われるようになってしまった感があります。
ただ、リマスターで音質はほとんど変わらなくても音圧(音の大きさ)が上がったことで、高音質になったと勘違いすることも多いです。
まあその辺は以前も書きましたがFoobar2000のリプレイゲインを使用し、ABXテスト機能で聞き比べてみればオーディオマニアでなくてもすぐにわかると思います。
24ビットのリマスター盤聴いてあまりの退屈さにびっくりしたニルバーナってこんなつまんない音だっけ、といそいでCD聞き直すとこっちはやっぱりいい。理屈はわかんないけど、新しい方聴いていいって言う人は耳か頭が腐ってんじゃないのってくらい違って、そんな情報探してこのブログを見つけました
レコード会社はたぶんニルバーナをこれ以上売りたくない、ティーンをオルタナティブロックに汚染したくないんだと思います。そうでなければあんなクズは速攻で産廃処分してる
同じマスタリングなら24ビットは16ビットのCDよりも理論上は高音質ですが、音圧を上げることや、重低音を強調するとか高音を目立たせるとかのイコライジングとはまた別問題だと思います。
好みに合わないマスターの24ビットよりも好みにあうマスターの16ビットの方を選択するのは素晴らしいことだと思います。