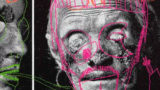Butthole Surfers 29曲(You Tube)
Butthole Surfers (バットホール・サーファーズ)の概要
テキサス州サン・アントニオで出会ったギビー・ハインズとポール・レアリーが1981年に結成したバンド。
Butthole(肛門)という言葉をバンド名に使用していることや、アルバムのジャケットが悪趣味なことからして、なんとなくどんなバンドか想像できるだろうか?
音楽性は、簡単に言ってしまえばBlack Flagなどのアンダーグラウンドなパンクと、The 13th Floor Elevatorsをはじめとする彼らの地元のテキサス州のサイケデリック・ロックとの融合といえる。
ただ浮遊感のあるサイケといっても狂人的で猟奇的。聞いているこちらの頭がおかしくなるような音楽だ。
またテキサス出身らしくカントリー・ミュージックからの影響もあるし、R.E.Mのような歌モノの要素も取り入れており、後期になるとポップ化、エレクトロ化していった。
音楽性もさることながら、変態、危険、下品、といった言葉を連想させる混沌としたライヴパフォーマンスと行動もこのバンドの魅力の一つだ。
サンアントニオの新聞が、僕らがオースティンにいるのを知ってライブ写真を掲載した。
僕は裸で腰に国旗を巻いている。しかもそれに火が。そんな写真を日曜版の娯楽面に載せたのさ。
「ロック史上最悪のバンド。」
しかも僕らの名前は「ケツの穴波乗り野郎ども」
Butthole Surfers / ギビー・ハインズ / Sonic Highways
主な奇行は裸になる、女装する、ストリッパーを出演させる、ライフルで空砲を撃つ、シンバルなどに火をつける、交通事故現場などの写真を映し出す、大量の洗濯バサミを服や髪につける、ぬいぐるみをばらばらにするなど。
1993年の大阪クアトロでの来日公演では、興奮してステージに上がってきた女性をギビーがぶん殴るという伝説を残している。
また、現在のところ最後の来日公演となっている2001年のフジロックではシンバルを燃やしていたとのことだ。
年齢制限のないショウに裸の女性を出演させる。
クラブのオーナーたちは当然それをやめさせようとする。
ギビーは怒って火をつけた。
LCD Soundsystem / ジェームス・マーフィー / Sonic Highways
このような常人離れした音楽と行動はテキサスという土地から生み出されたものなのだろうか?
やっぱ俺たち、テキサス出身だからね(笑)。アメリカじゃ、テキサスって変人の集まりみたいなところなんだよ。
めちゃくちゃ暑いから、みんな脳みそがどこかおかしくなってて……だから俺たちの音楽も、いつも他とはどこか違っていたんだと思う。
ニューヨークやロサンゼルス出身のバンドよりも、もっとだらけた、ヘンテコな音だしね。
キング・コフィー / クロスビート2001年11月号
1981年のバンド結成後、Dead Kennedysのジェロ・ビアフラのレーベルであるAlternative Tentaclesから作品をリリース。
その後Touch and Goに移籍してアルバムを次々とリリースし、奇抜なライヴパフォーマンスも評判を呼んだ。
1991年には第一回目のロラパルーザのメインステージに出演。1992年にはメジャーレーベルのキャピタルと契約を結んだ。
このような危険なカルト・バンドがメジャーデビューしたという事実はオルタナティヴ・ムーブメントを象徴していた出来事の一つだといっていいだろう。
1995年にタッチアンドゴーが過去の作品を効果的にプロモーションして売ろうとしていないとして訴訟を起こし、1999年に勝訴して作品の所有権はバンドのレーベルLatino Buggerveilが獲得し、再発されることとなった。
またキャピタルとも問題を抱え、1998年にはAfter the Astronautというアルバムのリリースを拒否され、2001年に他のレーベルからWeird Revolutionというタイトルでリリースされた。
以降はバンドとしての活動が徐々に下火となっていき、2023年現在では活動しているのかどうか不明となっている。
関連リンク
Butthole Surfers (バットホール・サーファーズ)のアルバム紹介
おすすめアルバム
個人的にはこれがベスト。
ヘヴィなLocust Abortion Technicianは最高傑作といわれることも。
メジャー時代ならこのアルバムがベスト。