コンニチハ、Helmetのペイジ・ハミルトンです。
自分の音楽を他人に何と呼んでもらいたいかなんて、心配することじゃないと思うな。音楽は音楽だ。
例えば、レッド・ツェッペリンは何だ? ハード・ロックもあったし、アコースティックな曲もあったし、サイケで暴力的なフィードバックもあったし、一言では言えない。とにかく偉大なバンドだった。
ロッキングオン1995年1月号から引用
Helmetのページの更新は順調に進んでいます。
そんな中でふと考えてしまったのが、Helmetのように90年代にオーバーグラウンド化した「ヘヴィ・メタルのようだが、従来のメタルとは何かが違う」というようなバンドのジャンルというか呼び名というかそういうのです。
個人的には、いわゆるジャンル分けの便利さは理解してはいます。特にこういう文章を書くときはジャンル名を書きたくなりますよね。ただここまで細分化されてしまうと呼び名にこだわるのはバカらしいと感じてしまうタイプの人間なんでどうでもいいって感じです。人によって解釈も違いますし議論が絶えないので面倒です。
これは「グランジとは?」に書きましたが、特定の音楽を示す言葉ではない「オルタナティヴ」という言葉は好きですけど、「グランジ」という言葉は嫌いです、あんなサイトを作っておきながらですが。
話を戻すと、そういうバンドたちの呼び名についてヘヴィ・ロックとかモダン・ヘヴィネスとかラウドロックとか、それこそグランジとか、単純にオルタナティヴとか思いつくわけですが、世間の考えをググって調査していたところ、どうしても納得できないことがありました。ラウドロックという言葉は和製英語という説明です。これはラウドロックのWikipediaに書かれているのですけど。
CMJ(カレッジ・メディア・ジャーナル)のLoud Rock Chartsというランキングはどう説明するんだよ!って突っ込みたくなりました。
海外のロックに関していえば英語版はともかく日本語版のWikiは、インターネット上に存在する情報の大洪水の中の一部分と思って、掲載されている情報をうのみにしない方がよいです。間違っているかもしれないと思うべきです。まあこれはうちのサイトやブログにもいえることですが。でもWikipediaというブランド力は絶大ですからねえ。
CMJがラウドロックチャートを始めたきっかけについてはクロスビート1991年6月号のニューヨーク在住の林洋子さんの記事を思い出しました。
ヘヴィ・メタルが母体になっていながら、ラップ、ファンク、サイケデリックetcが入っている音楽、様々な要素の一つとしてヘヴィ・メタルが入っている音楽をアメリカではどう呼んでいるのかと編集部から質問を受けたが、私の知るかぎり、決まった呼び方はないようだ。
クロスビート1991年6月号の新世代ロックバンドの台頭より
1991年前半の時点で、メタルのようだが今までのメタルとは違うバンドの一般的なジャンル名はアメリカにもなかったようです。ただし、とあるメタルラジオ番組のプロデューサーはFaith No Moreのようなラップやファンクを取り入れているバンドをファンク・メタル、サイケやアート色の強いJane’s AddictionやSoundgardenなどをオルタナティヴ・メタルと呼んでいたとのことですが、まあ一般的ではなかったので「決まった呼び方はないようだ。」とされたのでしょう。
その他にもクロスオーヴァーやネオ・メタルという言葉も紹介されています。
CMJのメタル部門は2年前(1989年)、ミュージック・マラソン・セミナーがあったとき、WE HATE HEAVY METAL AND HARD ROCKと宣言した。これは文字通りヘヴィ・メタル/ハード・ロックが嫌いになったという意味ではなく、HM/HRと呼ばれる音楽がそうした言葉が本来持っていたような狭い定義ではカバーできないくらい変化したからこの辺でHM/HRと呼ぶのはやめようという呼びかけであり、新しい認識を促したものだ。この時、彼らはこうした音楽を総称して「ラウドでアグレッシヴなギター中心のロック」と呼び、以来彼らはHM/HRセクションをAAGH!!(おそらく間違いでARGH!!が正)と名づけ、そのトップ100をラウド100と呼んでいる。
クロスビート1991年6月号の新世代ロックバンドの台頭より
おそらくこのLoud 100がLoud Rock Chartsになったのでしょうね。CMJはアンダーグラウンドにも精通していたでしょうから、早い段階からジャンルの壁を飛び越えるバンドを意識しており、ヘヴィ・メタルというジャンル名の限界を感じるのも早かったのでしょう。
CMJは1990年にLoud Rockという言葉が入ったコンピレーションをリリースしています。これがおそらくLoud Rockと題された初のアルバムでは?
CMJ Presents “ARGH!! It’s A Loud Rock CD!” – Vol. 1, July 1990 リンク先はDiscogs
Loud 100は1994年内にLoud Rock 75というチャートになり、しだいに40位までしか紹介されなくなりました。ARGH!!という言葉は消えていきましたが、Loud Rockという言葉はかなり頻繁に雑誌内に登場していました。
CMJのラウドロックチャートには、W.A.S.P.のような80年代のメタルバンド、Slayerのようなスラッシュメタル、デスメタルのNapalm DeathやCathedral、オルタナ系のNINやMinistryやRATM、ニューメタルやラップメタルと呼ばれたKornやSlipknotやLimp Bizkit、パンク、ハードコア寄りのBiohazardやSODなどがチャートにランクインしていました。これらのバンドを見れば当時のラウドロックの意味合いは大体理解できますよね。
ラウドロックチャートがいつまで続いたのかはよくわかりません。信じちゃいけない英語版のCMJのWikipediaによると雑誌としてのCMJは消滅したもののオンライン雑誌としては2017年まで存在したとありますが。
ともかくLoud Rockという呼び名は海外では主流にはなりえなかったようですね。ただ、ガラパゴス日本独自の進化を遂げたみたいなんで和製英語だと勘違いされたんじゃないでしょうか。日本では誰がいつどういう意味合いで使用し始めたのかはよくわかりませんが、CMJのラウドロックチャートというランキングを意識していたのは間違いないと思います。ビルボードには敵わないにしても、CMJのチャートも有名でしたしね。
カレッジラジオでのオンエア数を集計してチャートを作っていたCMJは、流行としてのオルタナが全盛期だった時代に重要な役割を果たしていましたから、メディアの人間にしろレコード会社の人間にしろ、90年代に洋楽ロック関連の仕事をしていた者がCMJを知らないってことはないでしょう。
特にシンコーミュージックから出版されていた音楽雑誌のクロスビートにはCMJの総合チャートが掲載されていましたから、シンコーミュージック系統の方がCMJを見たことがないとは考えられません。だからラウドロックの歴史を語るうえでCMJのラウドロックチャートは無視できません。
ラウドロックという言葉の持つ意味は、現在の日本でも昔と意味合いはあまり変わっていないのではないでしょうか。ロックはネタ切れで新しいものが生まれていませんしね。
結局、海外での「ヘヴィ・メタルが母体になっていながら、ラップ、ファンク、サイケデリックetcが入っている音楽、様々な要素の一つとしてヘヴィ・メタルが入っている音楽」の1991年以降の主流の呼び名は何だったのですかね? 今となってはオルタナティヴ・メタルとの説が強そうですが、私は海外在住でもなかったですし海外の雑誌を購読していませんでしたのでわかりません。古い雑誌を読んでいて何か情報を発見できればこの記事を更新します。
日本では「オルタナティヴ・メタル」なんて言葉を聞いた記憶がないです。まあ日本では「ヘヴィ・ロック」と「ミクスチャー」が主流だったといっておきましょう。昔はWikipediaに「ヘヴィロック」の項目か、独立した項目じゃないにせよどこかに説明があった気がするんですが、今では「ヘヴィロック」という言葉は存在しなかったかのような扱いですね。日本のメディアでは頻繁に見かけましたけど、こうして歴史は捻じ曲げられて伝えられていくのでしょう。恐ろしいですね。
雑誌としてのCMJはWorld Radio HistoryのCMJ New Music ReportやGoogle BooksのCMJ New Music Reportで読むことができます。ちなみにアイキャッチ画像は1999年6月21日号です。


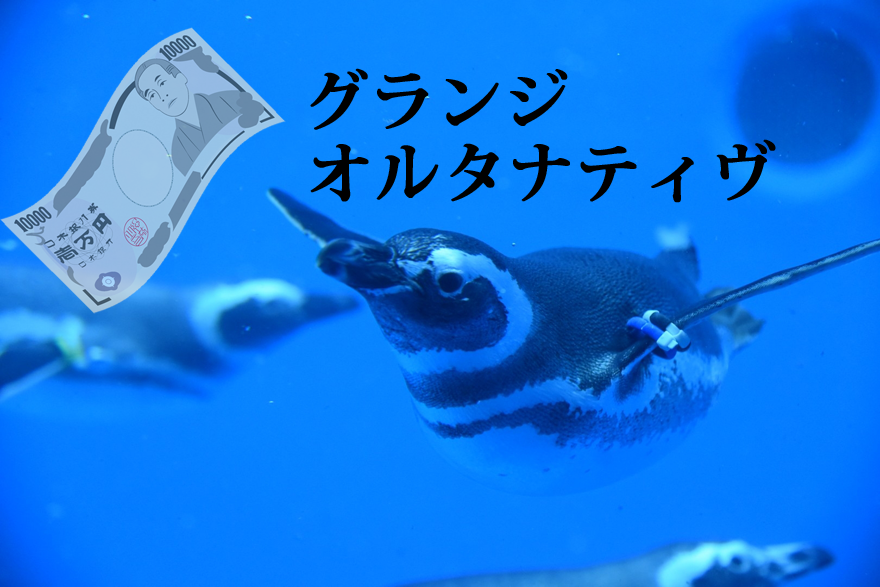


コメント