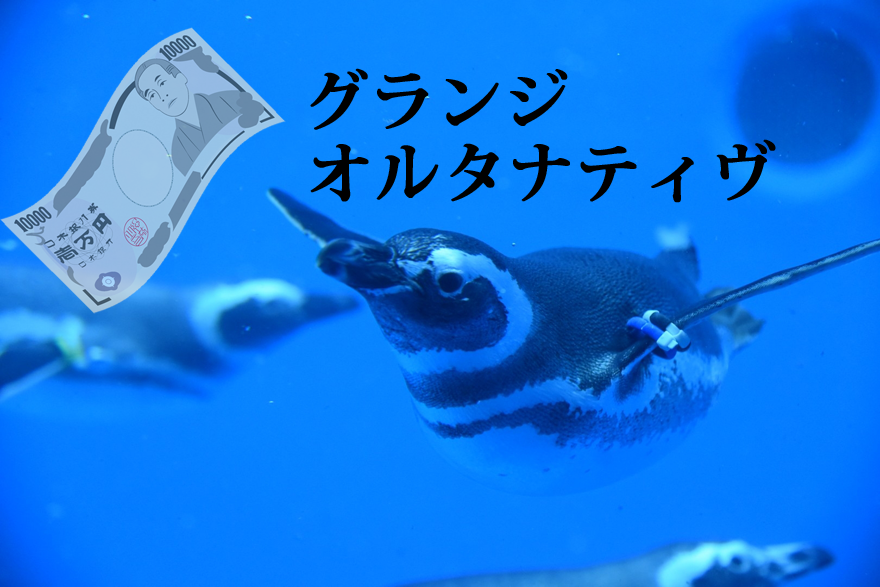Rollins Band 9曲(You Tube)
Rollins Band (ロリンズ・バンド)の概要
Black Flagが86年の7月に解散した後、Black Flagのヴォーカリストだったヘンリー・ロリンズは直ちにソロ活動を開始し、87年にRollins Bandを結成した。
音楽性はBlack Flag以上にハードロック・メタル色が強い。
単なるミドルテンポのメタルで終わらないのは、ハードコアを連想させるヘンリー・ロリンズの咆哮と、世間に上手く適合できないアウトサイダーの葛藤を描いたような歌詞によるところが大きい。
聞きやすいキャッチーなメロディは少ないので、ロリンズの叫びからリアリティを感じられるかが鍵となる。
またライヴパフォーマンスが凄まじかったようで、ロリンズのマッチョな肉体から放たれる本気度120%の咆哮にノックアウトされた人も多いらしい。
しかし後期になると、音楽性に工夫が見られる代わりに緊張感は後退し、単なるハードロック、ヘヴィメタルに成り下がってしまった感がある。
俺の中にあった、「俺はなんて哀れで可愛そうなんだ。」っていう感傷はどこかに捨ててしまったよ。
2001年 ヘンリー・ロリンズ
Black FlagやRollins Bandでの活動内容、贅肉を削ぎ落としたマッチョな肉体、禁欲的なライフスタイル、アンチ商業主義、時間を一切無駄にしない仕事依存症的な性格などから、一切の妥協を許さないハードコア精神を貫く、弱い心を持ちながらも鋼のような意志でそれを乗り越える頑固なパンクロッカーといったイメージがある。
しかし、「俺が会ったヘンリー・ロリンズは巷でいわれているような人間じゃなかった。」と苦笑するミュージシャンもいれば、日本のインタヴューアに「何で俺のコーヒーがないんだ!早く持って来い!いちいち言わせるんじゃねえ!」と吠えるロックスターな態度もエピソードとして残っている。
ロリンズ自身、彼の歌詞から読み取れる苦悩、苦闘といったイメージの多くはマスコミによって作られたと語っている。
(歌詞は)気分が良ければそれが反映されるだろう。
うわべだけの感情とか、ある種の(苦闘、苦悩)といったペルソナを映し出さねばならないとは思っていない。
2001年 ヘンリー・ロリンズ
Rollins Band活動当初はインディで活動していたが91年にメジャーレベルと契約、第一回ロラパルーザに出演したりと、徐々にメインストリームでも受け入れられていった。
バンドメンバーを総入れ替えしたこともあったが、2001年までにアルバムを7枚リリースしている。
その後は沈黙が続き、音楽活動はもうしないのではないかという噂もあった。しかし2006年に再結成ツアーを行っている。
ロリンズはワーカホリック(仕事依存症)と思えるほど音楽以外の活動も多かった。
2.13.61という出版社を設立し、エッセイや詩集、写真集をリリースしている。
意外なことに俳優業にもチャレンジしており、JMという映画ではビートたけしと共演している。
Rollins Bandの活動と並行してスポークン・ワード(詩の朗読、ジョークから社会的でシリアスなネタなどを扱う喋り芸)のツアーも行ってきた。
ヘンリー・ロリンズ名義でスポークン・ワードのCDやビデオもリリースしている。
ただし、英語のできない日本人にとっては理解不可能なのが残念だ。
2008年現在でもスポークン・ワードのツアーを敢行しており、こちらの方に力を入れているようだ。
2006年に再結成ツアーを行ったものの、アルバムリリースの話は聞こえてこない。
Rollins Bandとしての活動予定は全くわからない。
関連リンク
Rollins Band (ロリンズ・バンド)のアルバム紹介
おすすめアルバム
最も人気があると思われるアルバム。
個人的にはこれがベスト。